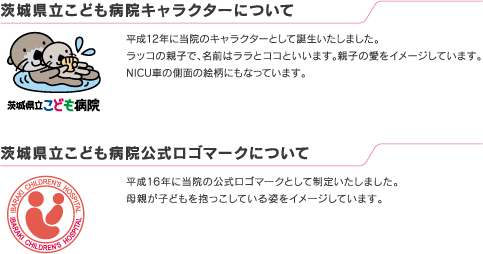COVID-19対策から医師の働き方改革への取り組み
院長に就任して2年間が経過しました。就任時にはまだCOVID-19が流行しており、その対応に追われました。PICU(当時はICU)の一部を陰圧化してCOVID-19に対応できるようにし、外来看護師の補充などを行ってきました。COVID-19は昨年5月8日から5類に分類され、通常の感染症とほぼ同様の対応になりましたが、小児にとっても重要な感染症として定着してしまいました。
就任2年目の重要な課題は、医師の働き方改革への対応でした。実際にスタートするのは本年4月からですが、当院のように救急部門が重要な役割を果たす医療機関においては、当直体制の再構築が必要となり、宿日直許可の取得や変形労働時間制の導入など、それぞれの当直形態ごとに対策を立てました。期待したような対応になるのか不安の残るところではありますが、関係者にご協力いただき、地域の小児・周産期救急を維持していくことが重要であると考えています。
少子化の中での当院の役割
茨城県でも少子化に拍車がかかっており、この10年間で出生数はおおよそ3割減少しています。特に最近5年間で出生数減少が進んでいることが心配です。出生数の減少は、直接的に新生児治療室への入院患者減少につながっています。有病率の減少ではなく、単に出生数の減少によるものであり、これは今後の小児診療全体にも影響してきますし、保育園や幼稚園の児童、さらに小学生の減少が進んでより大きな社会問題になると思われます。
この少子化の中で小児科医の役割も変化していくものと考えています。水戸市周辺の小児医療の状況をみますと、感染症の流行時には小児科開業医の予約はすぐに埋まってしまい、受診が難しくなるのが現状と聞いています。増加している発達障害児の受診を一次医療機関が対応するのは難しく、専門医療機関では初診まで数か月待ちの状態となっています。被虐待児の早期発見において小児科医の役割は大きいものの、現状ではあまり介入できていないと思われます。今後、1か月健診、5歳児健診も始まり、本来なら小児科医がかかわり、こどもたちがよりよい医療環境の中で育つことが理想であると思いますが、現在のところ、茨城県の小児医療体制ではそこまで対応できるとは言えません。小児科医の不足はまだ当分続くと思われます。また、何十年か先の小児医療の状況を予測するのは困難であり、当面は5年、10年先を見据えて、まずはその間に直面する問題を解決できるようにしなければならないと考えています。そして、小児医療の問題点を俯瞰して見られるのは、現場の小児科医たちです。今ある問題に対応しつつ、全体を見渡して地域の小児医療の今後の在り方についても提言していく義務があります。
経営改善と当院の役割
急激な少子化の進行は、当然、当院の経営にも大きな影響を与えつつあります。医療需要の変化に対応して、必要な医療を見直すなど、当院も変化していかなければなりません。その少子化の中でも、医療はさらに高度化、複雑化しており、今までの専門医療、救急医療も維持しつつ、医療的ケア児支援、虐待対応、移行期医療支援などに取り組んでいく必要があります。小児周産期医療の集約化が進む中で、小児医療の最後の砦としての役割を果たしつつ、経営改善にも職員一丸となって取り組んでまいります。
茨城県で安心して子育てができる環境作りに貢献していくため、今後もみなさまのご支援、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
2024年4月1日